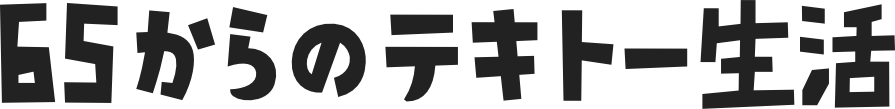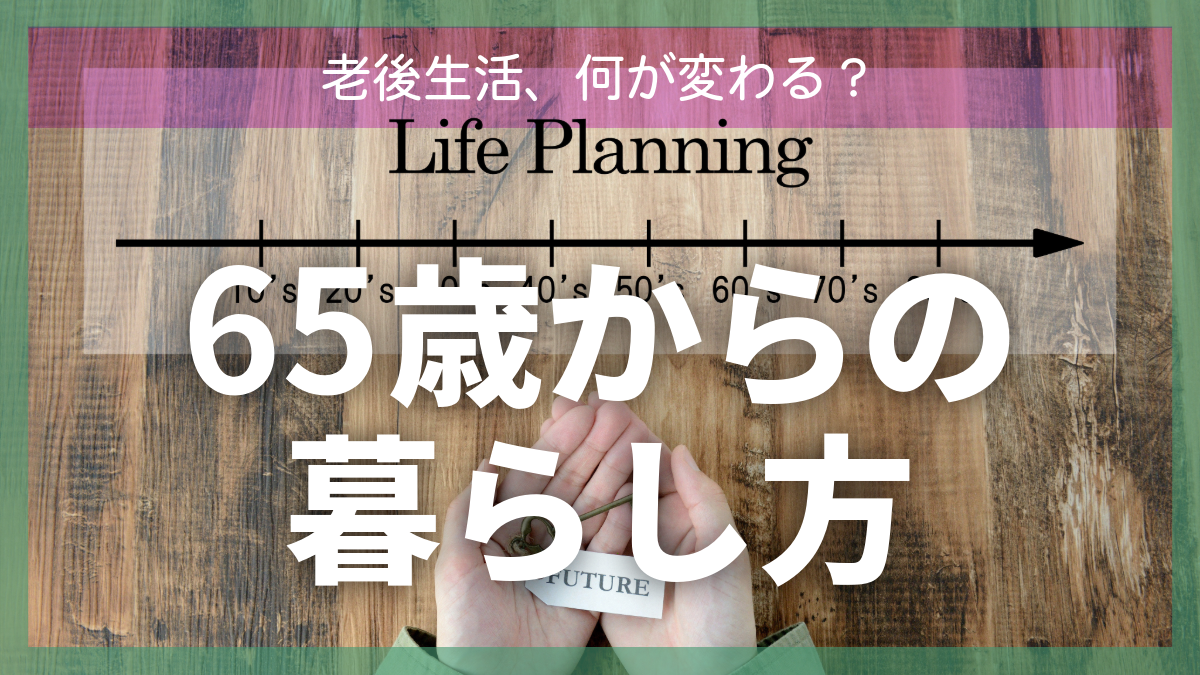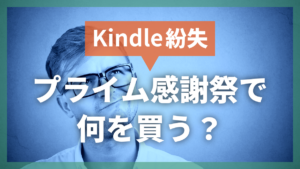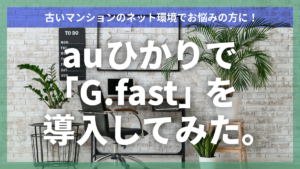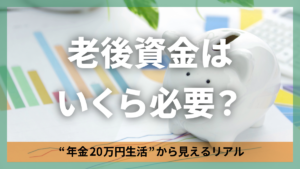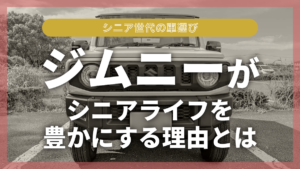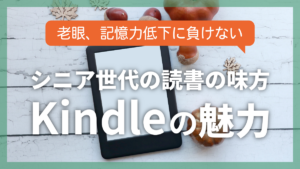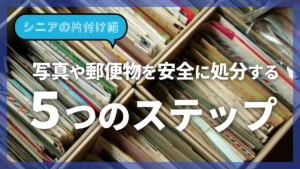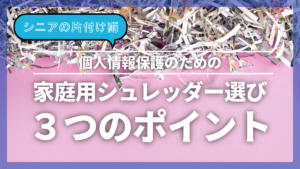本サイトは、65歳からの暮らしを取り上げていくブログです。
65歳という数字自体にこだわる必要はありませんが、多くの人が定年を迎えたり、年金の支給が開始されることを考えると、現役世代と老後生活の区切りとしてわかりやすい年齢には違いありません。
もちろん、もっと早い年齢で引退をしたり、まだまだ現役で働く人もいらっしゃいますが、社会的には「高齢者」として認識されます。
今回は、65歳という年齢のイメージや、そこから変わることについて考えてみたいと思います。
65歳、自分の感覚と世間のイメージ
「65歳になったら前期高齢者」。
この言葉を聞いて、どんなイメージを思い浮かべますか?
「高齢者」という言葉には、少し寂しさやネガティブな感情を抱いてしまうことも多いのですが、自分がその年齢になってみると、かつての「おじいちゃん」「おばあちゃん」という感覚はまったく持てません。
(子どもがいない、つまり孫もいない、ということもあるとは思いますが)
実際には世間からも、「まだまだ元気で若々しい」、「人生を謳歌している」というポジティブなイメージで認識されることが増えているようです。
私が好きな「ものまね芸人」で挙げると、男性では「コロッケ」、女性では「清水ミチコ」が65歳です。
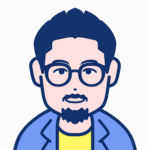
65歳は、人生の集大成でもなんでもない。
100歳まで生きたいと考えている人がどの程度の割合かはわかりませんが、平均寿命が80〜85歳とすると、まだ15〜20年は心も体も元気に暮らしていく必要があるのです。意外に長いですよね。
見方を変えれば、これまで培ってきた経験や知識を活かし、自分らしい生き方をデザインできる、最後のチャンスともいえるでしょう。
65歳からの老後生活、何が変わる?
65歳頃を境に、私たちの生活にはいくつかの変化が訪れます。
主な変化を3つの側面から見ていきましょう。
1.健康面
若い頃に比べて、体の変化を感じることが増えてきます。体力や筋力の低下、老眼や難聴など、身体機能の変化は避けられません。
しかし、人の細胞一つひとつにも寿命があるので、これは防ぎようがない流れです。自分の体と折り合いをつけることが大事で、無理のない範囲で健康管理を意識する良い機会と捉えるべきです。
いきなり強度のトレーニングをしても続きません。ウォーキングやストレッチなどの軽い運動を習慣にしたり、少しづつ栄養バランスに気を配った食事を心がけるようにしたいものです。


2.金銭面
多くの人にとっては、年金が主な収入源となる時期です。
たっぷりの貯蓄がある場合は別として、家計管理を見直す必要が出てきます。無駄な出費を抑える工夫(節約)をしたり、インフレに備えてある程度は資産運用を考える必要もあります。
また、社会保障制度の変化にも注目が必要です。医療費自己負担や介護保険料など、制度の変更点を把握しておくことが重要です。
3.生活面
私のように仕事から完全に引退する人も多く、生活リズムが大きく変わります。
朝の満員電車から解放され、自由に使える時間も増えるでしょう。この時間をどう過ごすかで、その後の暮らし方が決まると言っても過言ではありません。
脳は刺激を与えられないとどんどん劣化していきます。
今までの趣味や活動をさらに発展させていったり、新しいことを始めるいい機会でもあります。
心豊かに老後を過ごすためのヒント
変化の時期には、誰でも不安を感じるものです。
しかし、その不安を払拭するためのヒントがあります。
不安を受け入れ、希望に変える



これからどうなるんだろう?
そんな漠然とした不安を感じたら、まずはその気持ちを否定せずに受け入れてみたい。
そして、その不安を具体的に考えてみましょう。
「健康が不安」なら、健康診断を定期的に受ける、運動を始める、といった具体的な行動目標を立てることができます。「お金が不安」なら、家計簿をつけて収支を見える化する、専門家に相談するといった対策が考えられます。
漠然とした不安は、具体的な行動に落とし込むことで希望へと変わっていきます。
「生きがい」や「楽しみ」を見つける
生きがいは、人生に彩りを与えてくれます。それは、長年続けてきた趣味でもいいですし、まったく新しい挑戦でもかまいません。
例えば、以下のような新しい生きがいや楽しみを見つけてみるのもいいかもしれません。
- 学び直し:語学や歴史など、若い頃に興味があったことを改めて学んでみる。
- 社会貢献:ボランティア活動や地域コミュニティへの参加。
- 創作活動:俳句、絵画、手芸など、何かを「つくる」喜び。
ただし、ここで大切なのは、誰のためでもなく、自分が心から楽しいと思えることを見つけることです。
そのためには、無理をしない、ストレスをためない、ということが重要です。
デジタル社会を生き抜くためのリテラシー
現代社会は、スマートフォンやインターネット、AIの普及によって日々大きく変化しています。
高齢期の日常生活を困らないように過ごすためには、こうしたデジタル化の流れに取り残されないことが大切です。
世の中がインターネット時代へと大きく舵を切ったのは、Windows95が発売された1995年と言われています。
私が会社員から独立して飯を食べられるようになったのも、デジタル化やインターネットの普及が後押ししてくれたからです。その頃に30代後半の人たちが、現在は高齢者になり始めています。
進化し続けるデジタルの日常世界
現在65歳前後の人たちは、以前の「パソコンなどわからない」とか「携帯なんて電話でしか使わない」などと言っていた世代とは大きく異なり、パソコンも、ある程度の基本アプリやSNS、インターネットもそこそこ使えます。
しかし、デジタルの世界はあまりにも進化が速く、ましてやAI導入の日常化によって、少しでもそこから離れてしまうとあっという間にわからないことが出てきます。
例えば、日常生活で必要な電車のチケット購入や食事の支払い方法、マイナンバーカードのネット手続き、確定申告(e-Tax)など、ある程度のリテラシーをアップデートし続ける必要があるでしょう。
「一人では難しそう…」と感じる方もいるかもしれません。
そんな時は、自治体や地域の公民館が開催しているデジタル講座に参加してみるのがおすすめです。
詐欺やトラブルから身を守る
昨今社会問題となっていることのひとつは、ネット上での詐欺やトラブルです。
「AIがあなたの資産を増やします」といった甘い言葉や、身に覚えのない請求メールなどには注意が必要です。
基本的なルールとして、「怪しいと思ったらクリックしない」「個人情報を安易に入力しない」を心に留めておきましょう。困ったときは一人で抱え込まず、消費者生活センターや家族に相談することが大切です。
まとめ
65歳からの人生は、誰にも邪魔されない自分だけの時間でもあります。
不安を乗り越え、自分らしい生きがいや楽しみを見つけ、そして新しい時代に対応していくことが、心豊かな暮らしを築くための最善策といえるでしょう。