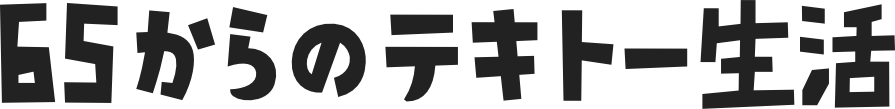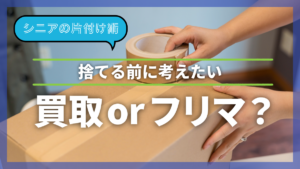遅ればせながら、映画『国宝』を観ました。
数年前に原作である小説を読んでとても感動していたので、それがどんな風に映像化されているのかをとても楽しみにしていました。
そもそも『国宝』とはどんな作品なのか?
『国宝』は、『パレード』や『横道世之介』などで知られる芥川賞作家・吉田修一氏の長編小説で、歌舞伎の世界を舞台に、芸の道に生きる人々の情熱や宿命を描いた作品です。
二部構成の壮大な物語で、華やかな舞台の裏にある人間の愛と苦悩、そして生き方を深く掘り下げています。
映画版では、この長大な原作を一本の作品にまとめており、上映時間は3時間を超えます。
それでも、豪華キャストが原作のキャラクターに息を吹き込み、華やかな舞台の世界を映像として再現していて、観客を退屈させない映像美と構成力があり、「長さを感じさせない」という声が多いのも特徴です。
ただし、映画と小説では描かれる範囲や重点の置き方が大きく異なり、それぞれ独立した作品として楽しめるように作られています。
映画『国宝』がロングラン上映を続ける理由
公開から数か月経っても上映が続いている、映画『国宝』。
3時間を超える長編にもかかわらず、その時間を感じさせないテンポと映像美で、多くの観客を魅了し続けています。
なぜここまでロングラン上映が続いているのでしょうか?
その理由はいくつか考えられます。
圧倒的な映像美と演技力
歌舞伎をテーマにした作品ならではの華やかな舞台シーンや、日本独特の美意識をとらえたソフィアン・エル・ファニのカメラワークは、スクリーンで観る価値を存分に感じさせてくれています。
また、ダブルキャストといってもいい人気若手俳優である吉沢亮と横浜流星をはじめとしたキャスト陣の演技力が高く評価されており、その迫力に引き込まれる観客も少なくないようです。
歌舞伎という日本の伝統芸能への興味
NHKの『芸能きわみ堂』という番組が好評を博しているように、これまで伝統芸能に触れてこなかった層が特に歌舞伎に対しての興味を引き起こしているともいえるでしょう。
歌舞伎の華やかさ、厳しさ、そしてその裏にある人間ドラマが、映像として丁寧に描かれていることで、歌舞伎ファンはもちろん、歌舞伎の新しいファンにも新鮮な感動を与えています。
原作小説の圧倒的な人気と評価
小説『国宝』は、文学的な深みと人間ドラマで高く評価された作品。映画化によって、その世界観を映像で体験できるとあって、原作ファンも足を運んでいます。かくいう自分もそのひとりです。
口コミやSNSでの評判が広がり、「もう一度観たい」とリピートする人も多く、結果としてロングランにつながっているようです。
どちらが先だと楽しめるだろうかという疑問
メディアやニュースサイト上では、映画を観た人の多くが「素晴らしかった」という感想を寄せていますが、SNSなどでは「わかりにくい部分があった」「つながりが見えづらい」「絶賛とまではいかない」という意見も見られます。
私の印象では、前者8:後者2くらいの比率です。
これは、映画が原作を大胆に取捨選択していることと関係がありそうです。小説と映画の両方を体験して、特にこの点に強く感じるものがありました。
そこで湧いてくるのがこの疑問です。
『国宝』は小説を読んでから映画を観るべきなのか、それとも映画を観てから小説を読むべきなのか?
この記事では、それぞれのメリットとデメリットを掘り下げ、あなたにとって最適な楽しみ方を見つけるためのヒントを提供します。
小説を読んでから映画を観るメリット
1. 深い世界観と登場人物への没入
小説は、登場人物の心情、背景、そして物語の世界観を詳細に描写します。
映画では描ききれない細部まで理解することで、より深い感情移入が可能になります。
2. 映像化された際の感動
小説で培ったイメージが、映画でどのように表現されるかを確認する楽しみがあります。
期待通りの場面や、想像を超えた演出に感動を覚えるでしょう。
3. 原作への敬意と理解
原作者が込めたメッセージやテーマを事前に深く理解することで、映画の監督や脚本家がどのように解釈し、映像化したのかをより多角的に評価できます。
映画を観てから小説を読むメリット
1. 純粋な映像体験
事前に小説を読んでいないことで、映像、音楽、俳優の演技から受ける感動がより新鮮で強烈なものになります。物語の展開に完全に没入できます。
2. 新たな発見の喜び
映画で物語の全体像を把握した後に小説を読むことで、映画では描かれなかったエピソードや登場人物の心の動き、伏線などに気づく喜びがあります。
3. 映画の視覚的イメージの定着
映画で見た俳優の顔や風景が小説を読む際のイメージとして定着するため、物語をより具体的に想像しながら読み進めることができます。
どちらを選ぶべきか?判断のポイント
1. あなたの読書・鑑賞スタイル
じっくり派:物語の背景や心理描写を重視するなら、小説から入るのがおすすめです。
直感派:まずは視覚的に物語を楽しみたいなら、映画から入るのが良いでしょう。
2. 時間の制約
小説は読み終えるまでに時間がかかります。
手軽に物語に触れたい場合は、まず映画を観るのが効率的です。
3. ネタバレへの耐性
映画を先に観ると、小説の主要な展開がわかってしまうことがあります。
ネタバレを避けたい場合は小説から読むべきです。
小説を読んでから映画を観た自分の場合
私は先に小説を読んでから映画を観ました。
ご覧になった多くの人たちと同様に、映像美も演技の迫力も素晴らしく、3時間超の長さをまったく感じさせませんでした。作品としての完成度は非常に高いと思います。
しかし、小説を読んでいたからこそ、映画で省略された部分がどうしても気になりました。
例えば、喜久雄の片腕でもある徳次の存在が冒頭だけで終わってしまうこと(とても重要な登場人物です)や、喜久雄の実の娘が終盤になってほとんど意味のない役柄で唐突に現れること。物語全体を知っていると、「あれ?ここ、重要なはずなのに…」と感じる場面がいくつもありました。
そのため、映画を観ながら「ここは省略しないでほしかった」「もっと丁寧に描いてほしかった」という思いが頭をよぎり、映像に完全に没頭しきれなかったのです。
【個人的なおすすめ】映画を先に観て、小説で深めるルートが最適
個人的には、小説を先に読むと、映画に対して少し残念な気持ちになる可能性があると感じました。
なぜなら、小説で膨大な背景や人間関係を理解した後に映画を観ると、「あの重要なエピソードが丸ごとない」というギャップが強調されてしまうからです。
一方で、映画を先に観ると、圧巻の映像美や演技を素直に楽しめます。
そのあとに小説を読むと「ああ、映画で描かれていなかったのはこういうことだったのか」と納得し、さらに深みを感じられます。
もちろん、映画と小説は別の作品です。その違いを受け入れられる人なら、どちらからでも楽しめるでしょう。
しかし実体験を踏まえると、この映画に限ってはとことわりを入れた上で、「映画 → 小説」の順番が、違和感を最小限にしながら両方を堪能できるベストなルートだと思いました。
まとめ
映画『国宝』は、映像美と演技力で観客を魅了する完成度の高い作品です。
しかし小説とは表現の方法も描かれる範囲も大きく違い、それぞれ独自の魅力を持っています。もしどちらも体験するなら、まずは映画で物語を新鮮に味わい、その後に小説で背景や人物の内面をじっくり深めていくのが吉だと感じました。
一度で二度楽しめる『国宝』、ぜひあなたなりのルートで堪能してみてください。
映画を観たあとに、ぜひ一読を!

俺たちは踊れる。だからもっと美しい世界に立たせてくれ!
極道と梨園。生い立ちも才能も違う若き二人の役者が、芸の道に青春を捧げていく。

鳴りやまぬ拍手と眩しいほどの光、人生の境地がここにあるーー。
芝居だけに生きてきた男たち。その命を賭してなお、見果てぬ夢を追い求めていく。