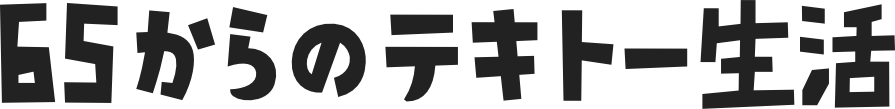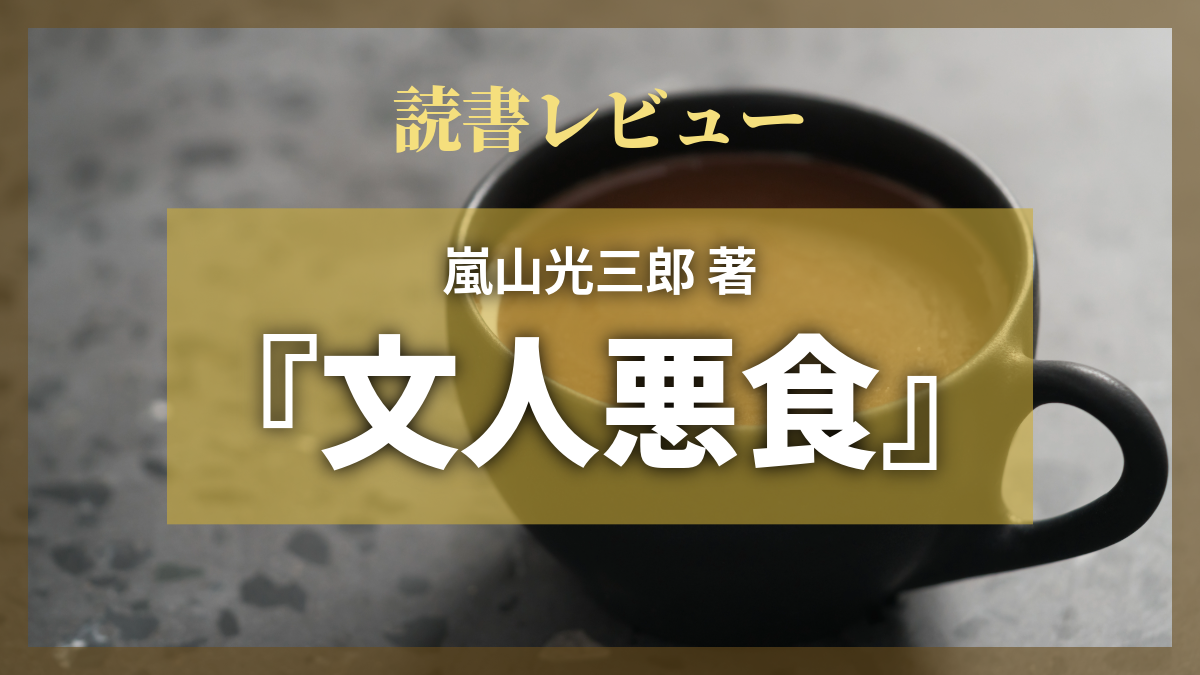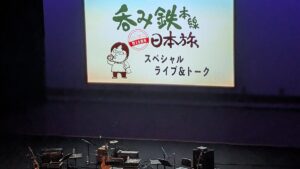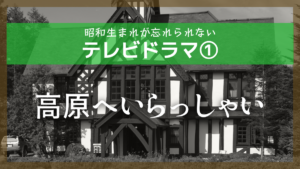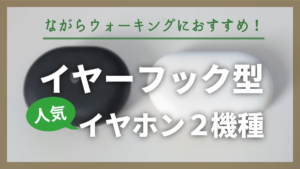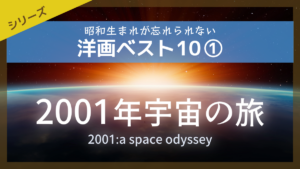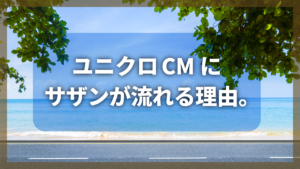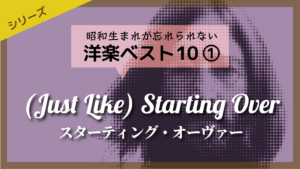好きな本の一冊に、嵐山光三郎の『文人悪食(ぶんじんあくじき)』があります。
文豪といわれた37人の作家の食生活が、作家自身の作品にどのような影響を及ぼしているかを、膨大な時間をかけて取材〜調査し、著者嵐山氏の主観をバリバリ交えてまとめあげた力作です。
単行本の初版は1997年に出ているので少し古い本ですが、久しぶりに読んでみました。
というわけで、今回は読書レビューです。
食通の文豪、偏食の文豪…? 活字でたどる作家の胃袋
本書には、夏目漱石から太宰治、川端康成、谷崎潤一郎、三島由紀夫といった錚々たる文豪たちが登場し、彼らがどのような食生活を送っていたのかが描かれています。
単なるグルメガイドではなく、食を通して文豪たちの人物像や作品の背景に迫っていきます。
例えば、太宰治が愛したカニやうなぎ、食が細かった川端康成の食の好み、そして谷崎潤一郎の作品にも登場する料理などが、当時の時代背景や文豪たちの人柄を交えながら語られます。
「食は人なり」。つまり、その人を知るなら、食生活を知るのが早道なのかもしれません。最近では「食育」という言葉もありますね。
幼い頃から食べてきた物、好き嫌い、食事の摂り方、誰と食卓を囲むかなどが、多かれ少なかれ人格形成に影響を与えるらしいのです。
ただし、それは一概に食べ物のせいだけとは言い切れない。そんなところに、人生の不条理みたいなものが見え隠れするんですね。
「食」に隠された意外なメッセージが面白い
例えば、石川啄木はその作風から、生家が貧乏で食べるものにも困って育ったようなイメージがありますが、実はそれほど貧しいわけではなかったということが知られています。
4人兄妹の唯一の男子だったこともあり、甘やかされてわがままに育ち、とても自己中心的な性格になったらしいのです。東京に出てからは本当に貧しくなった(笑)のですが、それでも我慢はせず、いろいろな人にたかっていたということです。
著者が啄木のことを書いている中で、次のような文章が出てきます。
啄木はハイカラである。辛酸をなめつくす貧困のなかからは啄木のようなハイカラな歌は生まれない。よく知られている「ココアのひと匙さじ」の詩がそうである。
はてしなき議論の後の
冷めたるココアのひと匙を啜すすりて、
そのうすにがき舌触りに、
われは知る、テロリストの
かなしき、かなしき心を。
この情景でテロリストが啜るのは、断じてココアでなければならない。テロリストなのだから、もっと安い渋茶であるとか、昆布茶、塩湯、甘酒、味噌汁、あるいは白湯さゆのほうが分相応という理屈は成立するが、この詩では、テロリストがココアを啜るからこそ、テロリストの孤独な匂いは伝わるのである。
嵐山光三郎『文人悪食』より
どうですか?
なんかゾクゾクするでしょう。
「啄木は東北生まれの貧しい苦労人」というイメージが音を立てて崩れるような、ね。
この本を読むと、後世に名を残す作家ほど、「変な人」「悪人」「性格破綻者」だったりするんだなー、と唖然としてしまいます。まずもって、清貧はいません。悪食で貪欲なのです。
凡人は、変人にこそあこがれる
作家に限らず、アーティスト、ミュージシャン、俳優など、エンターテイメントの分野で一時代を築くような人たちの中には、そういう人が多いんじゃないでしょうか。
発明家や革命家もそう。
エジソンやスティーブ・ジョブズだって、一般社会人としては変人ですよ。悪人と思っている人もいるはずです。
日本の映画黄金期のスターたち、例えば、萬屋錦之介や勝新太郎、石原裕次郎や松田優作だって、相当に変わり者だったという話です。
歌手・ミュージシャンもしかり。
ディック・ミネ、村田英雄、はてはマイケル・ジャクソンまで、みんな常識では考えられない逸話が残っています。この本にも出てくる、岡本かの子のご子息である岡本太郎もご覧のとおり。
その分野で一歩も二歩も抜きん出た存在にはそういう人が多いようです。
むしろ日常がそんなだからこそ、スターになったといえるのかもしれませんね。
なぜなら、我々凡人と同じような生活を送っている人が生み出すアート・芸を観たり聴いたりしたときに、「うまいね」と思うことはあっても、心の中に記憶としてずっと残ることは意外に少ないからです。
変な人が作るからこそそれは面白いし、輝いて見えるように思うのです。
人は本来、とんでもないヤツが書いた本を読みたいはずです。
まだ観たこともない個性をスクリーンに求めています。日常ではない、「ハレ」を観たいのです。
最近の文芸や芸能の世界にスターが現れなくなっているのは、日常が常識的な人ばかりが活躍できる風潮になったことに原因があると思っています。
メディアもわれわれ凡人も幼児化してしまい、魅力的という意味での「変な人たち」の出現を許さず、出る杭を打ち続けているのではないでしょうか。