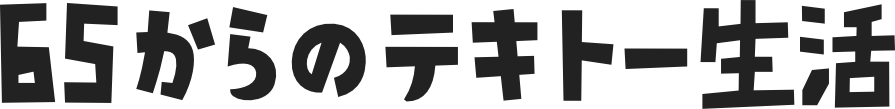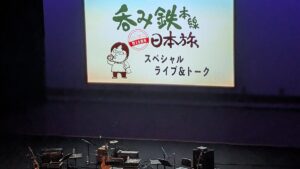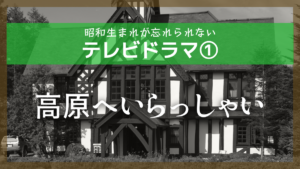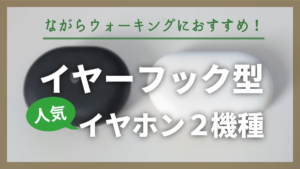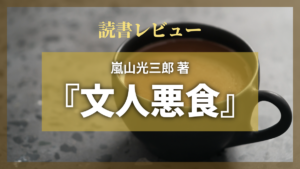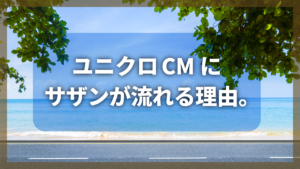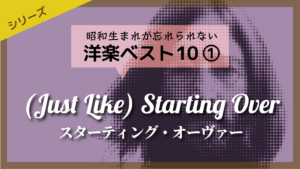昭和生まれが忘れられないシリーズ、今回は「洋画」です。そしてその第一弾は『2001年宇宙の旅』を取り上げます。
この映画はファンがとても多いので、本格的な内容紹介や解説をされている記事やブログが日本にはもちろん世界中に山ほどあります。
そんな先達以下の内容紹介しかできない私のようなものが字幅を割いても邪魔なだけですので、概要は簡単に述べるだけにとどめます。
※内容を知りたいのであれば、Wikipediaが手っ取り早いですしね。
知る人ぞ知る、SF映画の金字塔といわれている作品
『2001年宇宙の旅』は、アーサー・C・クラークの原作をスタンリー・キューブリック監督が手掛けた1968年公開、上映時間150分の作品です。
人類の進化をテーマに、謎の黒い石版「モノリス」と、宇宙船のコンピューター「HAL 9000」の反乱を描いています。セリフを極力抑え、映像と音楽で物語を伝える革新的な表現方法が特徴です。
こんなものでいいでしょうか?
というよりも、この映画をどんなにテキストで説明しても、その魅力を余すところなく伝えることは不可能です。
内職で忙しい母が手を止めた、衝撃のシーン。
1968年公開というと、今から57年前です。
でも、私が観たのはかなり後になってから、確か中学生の終わりごろ、50年くらい前でしょうか。
公開時だと9歳ですから、その存在すら知らなかったはずです。
映画館ではなく、テレビでした。(午後のロードショー的なやつだったと思います)
春休みで、小春日和の気持ちの良い居間の畳に胡座をかいて観たことを覚えています。
決して裕福ではない家でしたので、母は毎日縫い物の内職をしていました。
放映時も同じ居間の片隅で針仕事をしていましたが、私が観ていたテレビには何の関心も抱いていないようでした。
最初のシーン(あの映画史に残る問題のシーンです)が始まりました。
※まだ見ていない人、ごめんなさい。
セリフがまったくありません。
登場したのは「サル」たちです。いや「類人猿」と言っていいでしょう。人類の祖先ですね。当時の僕はそんな程度のボキャブラリーですよ。
突然、ものすごい鳴き声とともに争い(おそらく縄張りの)が始まり、殺し合い、勝ったものが生き残りました。
ふと、目の端に、針の手を止めてじっとこちらを見ている母がいました。
私のことではなく、テレビ画面を見ているのでした。
なにごとか、とでも思ったのでしょうか?
よくあるテレビ番組や映画では、絶対に出現しないような音と雰囲気。
ストーリーなどほとんど無いに等しいシーン。(よく考えればあるのですが)
画面には、次にいきなり黒い板みたいなものが現れました。
その場には絶対にあってはならないであろう人工物の形状で、それが後に「モノリス」というものであることを知ります。最初は「墓石」か「卒塔婆」か、と思ったものです。
母はまだブラウン管から目を離しませんでした。
というよりも凝視していた、という感じです。
そして、自分の息子は何を観ているんだろう、この内容がわかるのか?と思ったに違いありません。
自分の持っている「普通の映画」という価値観とはあまりにも異質な映像。
その時は「母さん、これはこういう意味なんだよ」といえるような知能を持ち合わせていませんでしたので、その後は何の会話もなく過ぎ去りました。おそらく今でも、気の利いた(母にわかるような)解説ができるとは思えません。
「モノリス」があらわれた瞬間、尻のあたりがザワザワしたのを覚えています。
デジタル?AI? そんな言葉はまだ無かった。
その後、数々の優れたSF映画があらわれた現在の感覚で言えば、特に若い人たちにとっては、ストーリーも映像もチープに見えるかもしれません。
実際に、この映画に影響を受けて誕生した『コンタクト』や『インターステラー』といった作品のほうが圧倒的に迫力があり、わかりやすくもできています。
でも、考えてみましょう。
公開当時には、「コンピューター」さえ一般化されていなかった時代です。CGやSFXなんてありえません。
「デジタル」という言葉の概念も定着していませんでしたし、ましてや現在普通に使われるようになった「AI」は言葉として欠片も存在していませんでした。
そんな時代に『2001年宇宙の旅』は、今の用語で言えば「AI」の反乱を描いたHAL 9000を通して、人工知能が持つ可能性と危険性を提示したんです。
急に難しいことを述べてみます。
この作品は、「AI」が倫理的に複雑な状況に直面したときにどう行動するか、そして人間と「AI」の関係はどうあるべきかという、現在の「AI」研究における重要な議論を先駆けて提起しているのではないでしょうか。
この作品を観た時に感じた「漠然とした不安な思い」は、50年後の今にしてやっと身近な出来事としてやってきました。多くの科学者や技術者がこの映画を、「AI」のような高度なコンピュータの世界に進むきっかけになったと語っているようです。
映像美と音楽について
その後、2018年に公開された『2001年宇宙の旅 HDデジタル・リマスター』をスクリーンで観ました。本当のデジタル技術による57年前の再現です。
まあ、これはある意味でやはり素晴らしいものでしたが、ね。